| サイトマップ | 利用規約 | プライバシーポリシー | 特定商取引に関する表示 |

雑談が苦手な人の多くは「自分には話題がない」と思い込みがちです。しかし実際には、雑談が得意な人ほど“話す型”を無意識に使っています。この「型」は、実はプロの文章作成でも活用されている会話の構造と同じです。
このページでは、雑談がうまい人の思考と技術を「代筆者の目線」から読み解き、明日から使える会話のヒントをお届けします。
◆このページのコンテンツ
多くの人が雑談を難しく感じる理由は、「目的がない会話」だからです。ビジネス会話のようにゴールが決まっている会話は設計しやすい。
しかし雑談には「何を話すか」が最初から決まっていません。そのため、自分の話をどう出すか、どこで相手に渡すかといった“進行のコントロール”が必要になります。
この操作感がつかめていないと、話が唐突だったり、独りよがりになったりして、相手が「つまらない」と感じてしまいます。
雑談がうまい人は「自然体で話しているように見える」ことが特徴です。ですが、それは単なる感覚ではありません。
彼らは知らず知らずのうちに、次のような会話構造を守っています。
これらは単なる会話の流れではなく、一種のストーリーテリングです。これはプロの代筆業において、「話し言葉に近い構文で書く」ための基盤ともなっています。
ここでは、実際に“話が続く人”が無意識に使っている会話パターンを5つご紹介します。これは、プロの文章家も使う「文章の骨組み」にも重なります。
どれも“完結しすぎない”ことがポイントです。余白や問いかけ、展開の余地があることで、相手の参加を促すことになります。これは、文章作成でも「読者を巻き込む書き方」に通じています。
雑談と文章。まったく別物に思えるかもしれません。しかし代筆の仕事においては、この両者は裏表の関係にあります。
読みやすい文章には必ず「話し言葉の構成」が隠れていますし、話しやすい会話にも「物語としての道筋」が含まれています。
例えば、以下のような意識は両者に共通しています。
プロの代筆者が文章を組み立てるとき、常に「これは声に出して自然か?」というチェックを行います。
それこそが「書きながら話し、話しながら書く」という技術であり、雑談力のヒントにもなるのです。
最後に、誰でもすぐに始められる雑談力アップの練習方法を紹介します。
雑談は、生まれつきの才能ではありません。
構造と視点さえわかれば、誰でも“話し上手”になれる余地があります。
そしてそれは、代筆ライターとしても“聴く力・書く力”を育てる鍛錬になります。
話す力と書く力を、同時に磨いてみませんか。
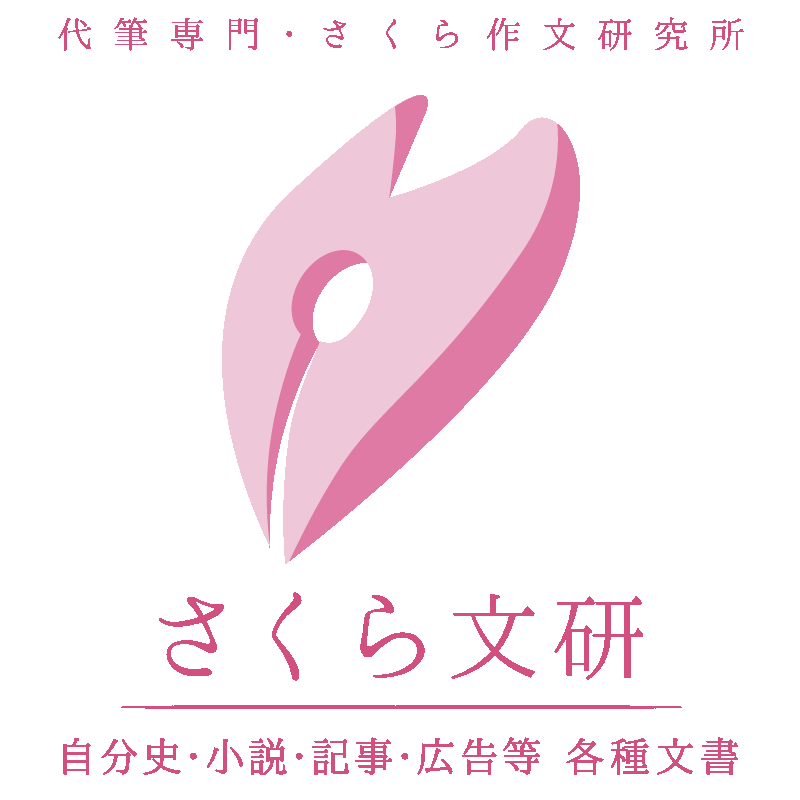 さくら文研<さくら作文研究所>は、様々なタイプの文章作成を代行する代筆専門サービスです。2014年の創業以来、文書作成の専門性を活かし、法人様・個人様を問わず、日本全国から寄せられる文章作成のご用命にお応えしてまいりました。
さくら文研<さくら作文研究所>は、様々なタイプの文章作成を代行する代筆専門サービスです。2014年の創業以来、文書作成の専門性を活かし、法人様・個人様を問わず、日本全国から寄せられる文章作成のご用命にお応えしてまいりました。
お手紙・各種作文・スピーチなど身の回りの原稿代筆から、自分史・オリジナル小説など長編原稿のゴーストライティング、企業の広告宣伝・コンテンツ作成などコンセプト企画まで、何でもご相談ください。
→さらに詳しく【事業概要】へ。
| サイトマップ | 利用規約 | プライバシーポリシー | 特定商取引に関する表示 |